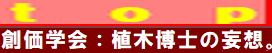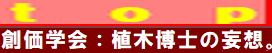
yahoo知恵袋から・・・
Q:空海は天才的な僧だったんですか?
A:空海さんは秀才ですが、唐の青龍寺には金剛頂経系の経典が揃っていませんでした、「不空翻訳:初会金剛頂経」です。全体の20%ぐらいしか空海は日本に持ってきていません。これを知っている人はあまりいません。空海伝説に水を差すようで申し訳ございません。完全翻訳は200年も後になってからです。しかし密教は金太郎あめのようなモノなのでそれでよいと思います。 |

●金剛頂経は、空海入唐以後、中国では、道教に押されて衰退するが、チベットではさらに追加・増広され発展する。
尚、円仁、円珍などが、後に空海請来目録の不足分を取りに、入唐する。
●「初会金剛頂経の完全翻訳」30巻は、比叡山の円仁・円珍よりもさらに後の宋の時代に「施護」が翻訳し、
施護は金剛頂経の14章・15章・16章も翻訳しています。
両部の大経
[大日経]
出典:wikipedia
『大毘盧遮那成仏神変加持経』(だいびるしゃなじょうぶつじんべんかじきょう)、
略して『大毘盧遮那経』(だいびるしゃなきょう)、
あるいは『大日経』(だいにちきょう)は、大乗仏教における密教経典である。
八世紀に、善無畏・一行の共訳による漢訳、
およびシーレーンドラボーディとペルツェクの共訳であるチベット語訳が相次いで成立したが、
梵文原典は現存しない。『金剛頂経』とともに真言密教における根本経典の一つとされる 。
漢訳『大日経』は全7巻36章である。このうち6巻31章が『大日経』の中核部分であり、
最後の第7巻5章は『大日経』に付属する供養儀軌である。
この第7巻の梵文原典は善無畏自身が北インドで入手したものであると考えられており、
『大日経』とは別個に存在する付属儀軌である。
チベット訳『大日経』も全部で36章よりなり、章数のうえでは漢訳と同じであるが、
チベット訳では最後の7章は護摩法などの手引きを書いた付属儀軌(uttaratantra. 続タントラ)であり、
本経(mūlatantra. 根本タントラ)には含まれない。
根本タントラの部分を比較したときに、漢訳『大日経』6 巻 31 章に対し、
チベット訳『大日経』は全部で7巻29章より構成され、漢訳より 2 章少ない。
漢訳もチベット訳も最後の部分は供養儀軌であるが、両者は相違し、
このチベット訳の供養儀軌に対応する漢訳は存在しない。
漢訳の第7巻に相当する部分は、チベット訳経典では『大日経』とは別個の儀軌になっており、
漢訳のように『大日経』に所属した儀軌ではない。
このように蔵漢両訳の文献に種々の胎蔵系供養儀軌が存在するということは、
インドにおいて『大日経』に基づく儀軌類が時代を経て改変・増広されていったということを示唆する。
チベット訳に記されているサンスクリット名は、
Mahāvairocana-abhisaṃbodhi-vikurvita-adhiṣṭhāna-vaipulyasūtra-indrarāja
nāma dharmaparyāya
(『大毘盧遮那成仏神変加持という方等経の大王と名付くる法門』)である。
成立時期
7世紀半の前後約30年間という栂尾祥雲1933年発表の説が一般に承認されている。
500年ごろにはすでに成立していたという説もあるが定説とはなっていない。
つまり、成立の過程が残っていない。
構成
漢訳『大日経』は、全7巻36品であるが、この内最初の第1巻から第6巻の31品が中核で、
第7巻5品は供養儀軌で善無畏が別に入手した梵本を訳して付加したものと見られている。
[金剛頂経]
これは、膨大な量だったと思われる。インドから、出発した金剛智の船団がペルシャ商船35隻の護衛のもと、
約20か国を経由し中国を目指した、
この途中、ジャワ島にも立ち寄っている。ジャワ島には密教が伝わっている。
また、中国西安青龍寺(空海上人が学んだ寺)では、ジャワ島の留学生を受け入れていた。
youtube【文学部】海がつなぐ世界-日本の密教は何処から来たのか-広島大学
https://www.youtube.com/watch?v=6-IWUO3nmQk&t=1s
金剛智は、風向きが変わるまでジャワ島で5か月間滞在している。
しかし輸送中、東シナ海において暴風雨に会い、船に積まれていた金剛頂経の広本と略本のうち広本を海中投棄した。
金剛頂経(広本)は、全部で18部あった、広義の金剛頂経というのは、偈頌からなる膨大な「経典群」であり、
単一の経典ではなく他の経典と重なる部分がある。
阿含経、華厳経、般若経、大集経、金剛頂経などは「経典群」と呼ばれる膨大な「追加経典」であり、
18部というのは、それぞれ別々の時代に別々の場所でつくられたお経が、まとめられたもので、
単一の計画性をもってつくられたお経ではない。その中には7世紀ごろに密教化した般若経典も含まれる。
18部あると言うのは、
金剛智から不空への口伝である「金剛頂経十八会指帰(ガイドブック)」によるものである。
※1.施護:
重要なヴァジュラヤナの語源テキストである金剛頂経(サルヴァタタガタ タットヴァサングラハ タントラ)は、
もともと紀元8世紀に不空(アモガヴァジュラ)によって中国語に翻訳されましたが、
不完全な翻訳でした。施護ダナパーラは、金剛頂経の18のセクションのうちの1番目、14番目15番目16番目を翻訳した。
wikipedia アメリカ版より
※2.『金剛頂瑜伽十八会指帰』「一切義成就品」の品題をめぐる一考察(秋山学)より
四大品より成るとされている『初会金剛頂経』の各品の名は、1 金剛界品,2 降三世品,3 遍調伏品,4 一切義成就品である。
すなわち、この「初会」のうち第四品の名が「一切義成就」である、もっとも『五秘密軌』は確かに不空訳ではあるものの、
不空は『初会金剛頂経』のうちの第一品である「金剛界品」、しかもそのうちの第一「金剛界大曼荼羅」のみを漢訳し、
「金剛界品」の第二「陀羅尼曼荼羅」以下に相当する部分、および第二品以降については訳出を果たさなかった、
したがって、同じく不空訳とされる『五秘密軌』において「一切義成就」という表現が見られることに鑑み、
先に『初会金剛頂経』の四大品の名を挙げる際に参照したのは、やはり不空の訳になるとされる『金剛頂経十八会指帰』であった。
[空海の請来目録について]
●空海請来の真言宗の不空翻訳の大教王経3巻本は、
初会しょえ金剛頂経(真実摂経しんじつしょうきょう)の金剛界品・降三世品・遍調伏品・一切義成就品
の四大品によって構成されているが、
各品には六種ないし十種のマンダラが説かれ、都合28種のマンダラが説かれている。
金剛界マンダラは金剛界品の最初に説かれ、これが二十八種のマンダラの基本となる。
正式には金剛界品のなかにある曼荼羅のうち、金剛会大曼荼羅のみしか翻訳されていない。
不空翻訳の金剛頂経第1部は、写本が無かったか、何らかの事情で、冒頭部分(金剛界大曼荼羅)しか翻訳できなかった。
●「金剛頂瑜伽中略出念誦」、またの名を「略出念誦経」空海が持ち帰っているが、
日本の正倉院にもあって、写経されていた。金剛智訳。
この本は不空翻訳の初会金剛頂経と若干範囲が異なるようである。
●「金剛頂経十八会指帰」は金剛頂経十八会の概要が書かれた本(ガイドブック)です。
これは金剛智から不空へ口伝で伝えられたものです。広本の金剛頂経は海中投棄されたからだと思われる。
●「大日経疏(だいにちきょうしょ)」、これは大日経の根本注釈書なるものである。
●「蘇悉地経」(蘇悉地羯羅経)とは、玄昉・最澄・空海らが請来した経典で、原版は善無畏訳。
●「理趣釈」、真言宗の主要経典。般若理趣分の略本で、不空訳、一巻。
十七段ある、「般若経」の一つで、「大般若経」の547巻の「理趣品」の発展形態である。
密教経典の一つとしてみれば、第六章の「金剛頂経」の一部(大楽最上経)とも解釈できる。
-----------ここからは、日本にもともと伝わっていたものです-----------
●「大日経」、大日経は空海以前から日本に伝わっており、正倉院にあり写経されていました。
その写本が久米寺にあり空海は入唐以前に、これを読んでいます。
●「金剛頂瑜伽略出念誦経」4巻本、これも空海入唐以前から正倉院にあり、写経されていました。
そして略出念誦経の範囲は、不空訳大教王経3巻本に近いです。
以上。
※ここに書かれているのは、根本経典に関する一部であり、空海は膨大な経典や注釈書、法具を持ち帰っている事は言うまでもない。
法華経に対しての言及、仮説、珍説、は多いが、浄土経典、密教に対する言及は少ない。アマチュア仏教研究家として、遺憾に思う事である。
※仏教学者あるいは、アマチュア仏教研究家の方に、確認と訂正、お願いします。訂正する場合、証拠文献を提示してください。