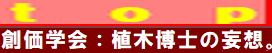
古寺散策 らくがき庵 https://mk123456.web.fc2.com/ 著者:堅田正夫
というホームページにおいて法華経の記述において間違いがあるのでここに示す。
禅宗、浄土真宗など、本来呪術性のない経典の宗派の方は、植木雅俊に騙されている。
■この堅田正夫という男は、植木の説を完全に信じている。或いは、植木の説が自分の宗派にとって都合がいいのであろう。
●間違いの部分は赤字で示した。
1. 法華経は一度に著述されたのではなく大乗を奉ずるグループに於いて段階的に著された様である 、従って後半部になる程、おとぎ話的な内容や二律背反的な思想が多く占める様になる と言う、本稿後半の法華経の案内●印でも扱うが、植木雅俊氏に依れば 「法華経の原型部分が成立した後、世間の人々の陀羅尼信仰、普賢信仰、観音信仰、阿弥陀信仰が流行した為に取り込んだ-- --」と言われる。
2.法華経には膨大な数の如来、菩薩達が登場するが地蔵菩薩の名前は無い と東京工業大学名誉教授・橋爪大三郎氏は言う。
3.法華本経の通常の構成は二門六段、すなわち目次は以下の様に分類。 前半十四品を迹門(しゃくもん)(釈迦如来(実在した釈迦)が仮の姿で衆生を導く)第一‐序品(序分) 第二‐方便品 第三‐譬喩品(ひゆほん) 第四‐信解品(しんげほん) 第五‐薬草品 第六‐授記品 第七‐化城喩品( けじょうゆほん ) 第八‐五百弟子受記品 第九‐受学入記品(~正宗分) 第十‐法師品(ほっしほん) 第十一‐見宝塔品(けんほうとうほん) 第十二‐堤婆達多品(だいばだったほん) 第十三‐勘持品(かんじほん) 第十四‐安楽行品(あんらくぎょうほん)(~流通分) 後半十四品を本門(久遠実成の姿で真実の法を説く)第十五‐従地涌出品(じゅうじゆじゅっぽん)(序分) 第十六‐如来寿量品(にょらいじゅりょうぼん) 第十七‐分別功徳品 (ふんべつくどくほん)(~正宗分) 第十八‐随喜功徳品(ずいきくどくほん) 第十九‐法師功徳品(ほっしくどくほん) 第二十‐常不軽菩薩品(じょうふきょうぼさつほん) 第二十一‐如来神力品(にょらいじゅりょうほん) 第二十二‐嘱累品(ぞくるいほん ) ●第二十三‐薬王菩薩本事品(やくおうぼさつほんじほん) ●第二十四‐妙音菩薩品 ●第二十五‐観世音菩薩普門品(普門の意味注25) ●第二十六‐陀羅尼品 ●第二十七‐妙荘厳王本事品(みょうしょうごんのうほんじほん) ●第二十八‐普賢菩薩観発品(~流通分) 、また序品に依れば法華三部経と言われる「無量義経・三品」「法華経」「普賢観経」がある、大名行列に例えれば法華経(大名)を中心に無量義経は開経と言い先導を務める経典で普賢観経は最後尾を務め結経と言う、普賢菩薩観発品に付いて漢訳では「善男子、善女子」に対して説かれているが梵語原文では即ち「女人達」に付いて説かれているだけである 。 ●印六品は後日に付加された品とされており哲学も文体にも相違が観られると言う、付加された六品はインドで興隆するヒンドウー教の影響を加味している様子である、諸経の王とも言われる法華経の人気は第二十五‐観世音菩薩普門品を初めとする後付加された六品の思想からと言えよう。梵語経典は複数存在したとされ鳩摩羅什は初期の経典を漢訳したと推定されている、因みにケルン・南条本とは品の順序に相違があるとされる。また「ほんとうの法華経」の著者、植木雅俊氏曰く”諸写本間の異同は複雑を極め、体系的に分類することは不可能に近い” と言う。端的に言えば迹門(実在し80歳で入滅した釈迦の教え 迹とは跡、足跡を意味)では総てに人は仏になれると説き、本門(久遠実成の釈迦の教え)では釈迦の命は久遠実状、すなわち昔から永遠であり80歳で死亡したのは方便であると説いている、閑話休題、迹門、本門の区分は梵語原典には存在しない、区分したのは天台智顗による。