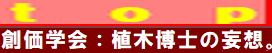
下記のようなデマをまき散らす輩が多いのでご注意を・・・
法華経は二十二品 浅きを去って深きに就く - 楽天ブログ 引用 https://plaza.rakuten.co.jp/karagura56/diary/202202200000/
中村元(仏教学者/浄土真宗)
植木雅俊:『法華経とは何か その思想と背景』
中央公論新社,2020.11
間違いは赤で修正しています。
法華経は二十二品 (二十七品)
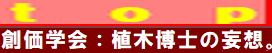
下記のようなデマをまき散らす輩が多いのでご注意を・・・
法華経は二十二品
浅きを去って深きに就く - 楽天ブログ 引用 https://plaza.rakuten.co.jp/karagura56/diary/202202200000/
中村元(仏教学者/浄土真宗)
植木雅俊:『法華経とは何か その思想と背景』
中央公論新社,2020.11
間違いは赤で修正しています。
法華経は二十二品 (二十七品)
『法華経』は釈尊滅後五百年経ったころに編纂されたものだが、釈尊が弟子(仏弟子・菩薩・ヒンドゥ教の神・土着神)に教えを説いて聞かせるという体裁をとっている。(法華経の説法の場に集まっている者の中心は仏弟子ではない)
表1の最上段の列にあるとおり、釈尊が教えを説いた場所の設定は、はじめは霊鷲山という小高い山であった。これは実際にインドにある高さ数百メートルほどの低い山である。第11章=見宝塔品(第十一)から空中(虚空)に移り、最後にまた霊鷲山に戻ってくる。
「ケルン・南条本」では、第27章となっている嘱累品で滅後の弘通の付嘱(『法華経』を布教する資格の付与)が終わった後に霊鷲山に復帰するが、復帰後の説法はないので(ある)“二処二会”の形になっている。鳩摩羅什訳では、嘱累品が第二十二(鳩摩羅什が移動)となっていて、その後に続く六品は霊鷲山で説かれたことになるので、説所は「霊鷲山→虚空→霊鷲山」と “二処三会”(二幕三場)の形式になっている。ただし、原形部分(原型?)だけ見れば“二処二会”(二処三会)である。表1の真ん中の列がサンスクリットの「ケルン・南条本」の章立て、下段の列が漢訳の鳩摩羅什訳の章立てである。見て分かるとおり、第11章の途中から両者で章立ての番号がずれている。これは、漢訳の提婆達多品第十二に当たる箇所が後から追加される際、それを第11章の続きとするか、単独の章として入れるかで違いが出たためである。
また、「ケルン・南条本」で第27章になっている嘱累品は、漢訳(鳩摩羅什訳)では第二十二となっている。『法華経』の原形(原型?意味不明)は嘱累品第二十二で終わっていたようだが、(終わっていない)後になって第21章=陀羅尼品(第二十六)、第22章=薬王菩薩本事品(第二十三)などの六つの章がそれに続けて追加され、(追加されていない)鳩摩羅什はその形式の写本から漢訳した。(その様な写本は、考古学的にも、記録にもない)その後、経典における嘱累品は通常は経典の最後に来るものだという理由から、(元々最後にあった)追加された(追加されていない)六つの章の後ろに移されて、(逆である)最後の第27章になった。このような事情により、章(品)の数字が前後している。(デタラメを言うな!嘱累品を移動したのは鳩摩羅什である)
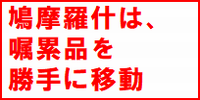
この先、本書において『法華経』を引用する場合、サンスクリット語の現代語訳は、角川ソフィア文庫の植木訳『サンスクリット版縮訳法華経現代語訳』(以下、『サンスクリット版縮訳法華経』)により、漢訳の書き下しは植木訳『梵漢和対照・現代語訳法華経』上・下巻
(岩波書店)を用いる。章名はよく知られた漢訳名を用い、たとえば第15章=如来寿量品(第十六)というように、漢訳の品の番号を漢数字で、サンスクリット版の章の番号を算用数字で記すことにした。
後半に追加された六つの章について補足すると、実はこれらは、『法華経』本来の内容(本来?) とは異質のものである(同質ものである)。庶民受けを狙って、現世利益や神がかり的な救済が説かれている。(法華経は全章が神がかり的)『法華経』本来の思想(法華経本来の思想?)を歪めるものであって、筆者としては、ないほうがよかったのではないかと思う箇所もある。▲植木の個人的願望。
中村元博士は、こうした事情を次のように述べておられる。要約して引用する。
特に初期の大乗仏教では、民衆に対して積極的に教化を行なうことに努める気運に満ちていた。けれども、当時の愚昧な一般民衆を教化するのは容易でないことを痛感した。民衆は、依然として昔ながらの呪術的な信仰をいだいていた。仏教は、当初から呪術・魔術の類を認めなかったので、一般民衆にはどうしても近づきがたいところがあった。大乗仏教(密教も)では、いちおう呪術的な要素を承認して、ダーラニー(陀羅尼)、すなわち呪文の類を多く作るとともに、当時の民間信仰をそのまま、あるいは幾分か変容して取り入れた(法華経の場合全面的に取り入れた) (『古代インド』講談社学術文庫、368~369頁)
この考えに従えば、『法華経』の高尚な平等思想などよりも、神通力などのほうに関心が強い庶民に媚びて、(法華経は全章が神通力)六つの章が追加されたという面もあるであろう。(追加されていない)最後に追加された六つの章は、(追加されていない)こうした妥協の産物的な要素が強いと思う。(妥協ではなく本望)たとえば薬王菩薩本事品第二十三での焼身供養(焼身自殺)を「最高の供養」として宣揚するのはいかがなものかと思わざるをえない。(いかがであっても関係ない)
以上のことを念頭に置いて、『法華経』の各品(以下、提婆達多品を追加した現行『妙法蓮華経』の品数で表記する)の成立順序について考えてみよう。それについては、提婆達多品を除くすべての品が同時に成立したというものもあれば、大きくは三段階を経て成立したというものまで、諸説紛々としている。その中で最も支持されているものは、(支持されているもの?)薬草喩品の後半部と提婆達多品を除いた序品から如来神力品までと、それに嘱累品を加えたものが『法華経』の原形(原型?) で、それ以後の六品、および薬草喩品の後半部と、提婆達多品が後世の付加(付加?)
であるとするように、大きく二つに分けるものである。そのうえで、さらにその原形(原型?)の部分を法師品の前で区切られることが多い。したがって、次の三類に分類されている。
下記は法華経以外の経典の価値を上げようと画策する下劣な学者の分類法である。
第一類=方便品第二~授学無学人記品第九
第二類=序品第一と、法師品第十~嘱累品第二十二(提婆達多品第十二は後世の付加)
第三類=薬王菩薩本事品第二十三、妙音菩薩品第二十四、観世音菩薩普門品第二十五、陀羅尼品第二十六、妙荘厳王本事品第二十七、普賢菩薩勧発品第二十八
この三段階を経て、順次に成立したとするものである。第一類と第二類のあいだの区分の理由は、第一類が声聞(男性出家者)(フィクション)を対告衆 (教えを説く対象)としていて、その未来成仏の予言(授記)(授記は神通力)
がテーマになっているのに対して、第二類では、菩薩が対告衆であり、釈尊滅後の法華弘通の資格を付嘱することがテーマになっていて、主題が異なるからだという。
筆者は、第一類、第二類で取りあつかわれる内容の違いは認められるとしても、(法華経の構成)
成立時期まで違うとする以上の考えに納得できない。対告衆を声聞と菩薩と異にしていることは、必ずしも経典成立の時間差とは決めがたい。後述するように、小乗と大乗の止揚として声聞と菩薩に対して区別することなく、「菩薩のための教え」である『法華経』が説かれているという視点を持てば、対告衆の違いは何ら問題ではなくなるのだ。(法華経の対告衆は全てフィクション)それにともない、第一類と第二類を一貫させるために序品第一が作られたとして、(その方が都合がいい)
第二類に分類する必要もなくなる。
また、第一類が、釈尊の遺骨を安置したストゥーパ(舎利塔)に対する崇拝を礼賛しているのに対して、第二類は、舎利塔でなく経典を安置した経塔に対する崇拝を強調しているという違いをとらえて、(インドではストゥーパとチャイトヤは同じ意味として使われる)
成立時期の時間差を見出そうとするものもあるが、『法華経』より先に成立していた『般若経』がすでにストゥーパ信仰を批判するとともに経典重視の思想を打ち出しており、そのことをすでに『法華経』編纂者たちは知っていたはずである。したがって、第一類、第二類におけるストゥーパに対する態度の違いは、経典成立の時間差を意味しているのではなく、ストーリー展開の順序にすぎないのではないか。したがって、筆者は、第一類と第二類は、多少の時間差はあるかもしれないが際立った時間差とは言えず、必ずしも分ける必要はないと考える。
(時間差無し)
むしろ、この二つに比して、第三類との段差のほうが内容的にも成立時期としても遥かに大きいと言わざるをえない。(ありえない学説。竺法護訳(西暦286年)にはすでに第三類がある)
そこには男女の産み分けや、ダーラニー
(陀羅尼) 信仰などインド土着の民間信仰や、現世利益のようなものまで『法華経』の名前でとりこまれていて、 (法華経の名前で?)原形部分(原型?) との違いがあまりにも大きすぎる。
第一類、第二類(仮説)を読んでいて、いつしか「自分が菩薩として何ができるだろうか」「何かしなければ」という能動的・積極的な思いに駆られるのに対して(じつにわざとらしい。最低の学者。クズ野郎。元浄土真宗の創価学会。)第三類、特に第24章=観世音菩薩普門品
(第二十五)を読んでいると、いつしか「観世音菩薩は私に何をしてくれるのだろう」「いつ助けに来てくれるのだろう」といった受身の姿勢に転じていることに気づく。(観世音菩薩を法華経から分断するための屁理屈)
その違いは大きい。
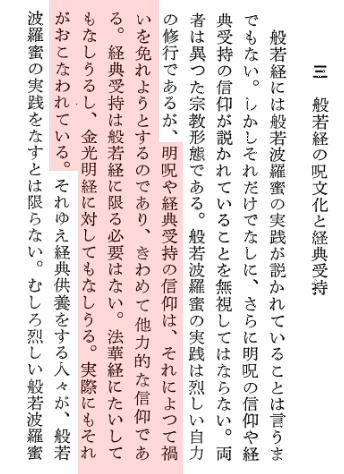 平川 彰東京大学 1971 年 19 巻 2 号 p.
584-592
平川 彰東京大学 1971 年 19 巻 2 号 p.
584-592
本書の「III『法華経』各章の思想」を論ずるところで、『法華経』を大きく分ける際に、この第一類、第二類、第三類という分け方を採用した。ただ、第1章=序品(第一)だけは、第二類から第一類に移して論じる。それは、成立順ということではなく、(成立順である) 内容面(内容面?)
の違い。 で分類したものである。これは法華経以外の経典の価値を上げようと画策する下劣な学者の分類法である。
【解説】
むしろ、この二つに比して、第三類との段差のほうが内容的にも成立時期としても遥かに大きいと言わざるをえない。(大きくない)そこには男女の産み分けや、ダーラニー (陀羅尼)
信仰などインド土着の民間信仰や、現世利益のようなものまで『法華経』の名前でとりこまれていて、(法華経の名前で?法華経だもん)原形部分(原型?)
との違いがあまりにも大きすぎる。
(法華経の原形部分とは何か?考古学的証拠がない)
ちなみに、気楽非活さんがいちゃもんを付けた根拠となる「薬王品」(「薬王菩薩本事品第二十三」は第三類に属します。
いくら「法華経」の一部だといっても、(壱部です)「法華経」の思想から大きく外れた内容も書いてある可能性があります。(法華経の思想?)
(「薬王菩薩」は法華経を供養するために「焼身自殺」した法華経の中でも最も尊い菩薩である)
【最後に】
法華経は現世利益!!
【法華経とは何か その思想と背景】植木雅俊著/中央公論新社刊
------------------------------------------------------------------------------
植木雅俊『法華経とは何か その思想と背景』(中央公論新社、2020.11)
(目次)
はしがき
Ⅰ 『法華経』の基礎知識―インドで生まれ、中国から各地に伝えられた経典
1)題号の意味
2)サンスクリット原典と翻訳
3)構成と成立順序
4)日本文化への影響
Ⅱ 『法華経』前夜の仏教―原始仏教から小乗、そして大乗の興起へ
1)原始仏教の権威主義化
2)小乗仏教の差別思想
3)大乗仏教の興起
Ⅲ 『法華経』各章の思想―「諸経の王」の全体像
1)あなたもブッダになれる(序品と第一類)
2)菩薩としての使命(序品を除く第二類)
3)民衆教化のために付加された六章(第三類)
Ⅳ 『法華経』の人間主義―“偉大な人間”とは誰のことか
1)人間としての釈尊
バリバリの法華宗檀家による植木雅俊の批判。法華経に関しては仏教研究家植木雅俊の独断場と化している。分身思想の黙殺や観音信仰、ダーラニーなど。2)人と法
3)永遠の菩薩道
あとがき
一部、引用します。
Ⅰ 『法華経』の基礎知識―インドで生まれ、中国から各地に伝えられた経典
2)サンスクリット原典と翻訳
□漢訳の「六訳三存三欠」
□サンスクリット原典写本の発見と校訂・出版
□梵文『法華経』現代語訳の四段階
□「ケルン・南条本」の汚名返上
□諸サンスクリット写本、諸翻訳間の異同
3)構成と成立順序
■『法華経』各品の成立順序
□一世紀末から三世紀初めの成立
□西北インドでの編纂
□法華経を編纂/信奉した人たち
□『法華経』実践者たちの実像
『法華経』各品の成立順序
「ケルン・南条本」と鳩摩羅什訳の『法華経』の構成を比較すると、次頁の表1のようにまとめることができる。