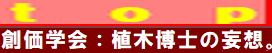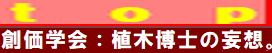
文殊菩薩は、法華経が起源である。

文殊菩薩 - Wikipediaから
『文殊師利般涅槃経』によると、舎衛国の多羅聚落の梵徳という
バラモンの家に生まれたとされる。また『
大智度論』によれば、
釈迦如来の滅度後に
弥勒菩薩と阿難と共同して
大乗経典を結集したとされる[注
1][4]
。『維摩経
』には、
維摩居士に問答でかなう者がいなかった時、居士の病床を釈迦
の代理として見舞った文殊菩薩のみが対等に問答を交えたと記され、智慧の菩薩としての性格を際立たせている。この教説に基づき、維摩居士と相対した場面を表した造形も行われている。
文殊菩薩が登場するのは初期の大乗経典、特に般若経典
である。ここでは釈迦仏に代って般若の「
空(くう)」を説いている。『華厳経
』では
善財童子を仏法求道の旅へ誘う重要な役で描かれることなどからもわかるように、文殊菩薩の徳性は悟り
へ到る重要な要素、般若=智慧である。尚、本来悟りへ到るための智慧
という側面の延長線上として、一般的な知恵
(頭の良さや知識が優れること)の象徴ともなり、これが後に「三人寄れば文殊の智恵」という
ことわざを生むことになった。
上記に対する反論
まずはじめに、般若経と文殊との関係について一言しておきたい。一般には、文殊菩薩は悟りの智慧を現わす菩薩であると見られ、般若波羅蜜と密接な関係があると見られているようである。すなわち文殊菩薩は般若教徒によつて信奉せられ、発農せしめられたと考えられやすい。しかし実際には、文殊菩薩は古い般若経とは関係が少いのである。それゆえ般若経の中から、文殊菩薩が現れたとは考え難い。
大乗仏教の興起と文殊菩薩 平川彰 引用