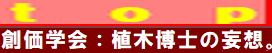
第五十九話 大勢至菩薩がなぜ『法華経』に
創価学会員のホームページ: 浅きを去って深きに就く - 楽天ブログの誤りを正す。
予備知識
| 出典:法善寺 上野 _ 日本 _ Houzenji 前記(省略)まずこの『観無量寿経』ですが、日本に伝わってきたものは?良耶舎(きょうりょうやしゃ)という方が訳されたものになります。サンスクリット語の原典があると言われていますが、今日に至るまで未だに見つかっていません。一説によれば原典は存在せず、中国で作られたお経とも言われています。 |
|
wikipediaから・・・勢至菩薩 概要 阿弥陀三尊の右脇侍。『観無量寿経』の中には「知恵を持って遍く一切を照らし、三途を離れしめて、無上の力を得せしむ故、大勢至と名づく」とあり、火途・血途・刀途の三途、迷いと戦いの世界の苦しみから知恵を持って救い、その亡者を仏道に引き入れ、正しい行いをさせる菩薩とされる。 |