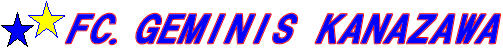
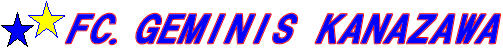
| Half-time No.21 1999年10月3日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
半年ぶりの「Half-time」の発行である。出さなければならないと思いながらも、私自身の職場の人事異動 も重なり、3学年揃ったGEMINISのクラブ運営に精一杯で時間的、精神的な余裕がなかったことが原因であり、自分の 能力の低さを情けなく思っています。今号は、メモと記憶を頼りにこの半年を振り返ってみたいと思います。 ★3期生・入団 「初心忘れるべからず」 4月に元気な現1年生(3期生)が入団し、3学年が揃ったGEMINISの11年度の活動がスタートしました。 3期生については、クラブの活動になじむことや、チームメイトとのコミュニケーションをとることにも気を使わなければならず、入団当初のトレーニングでは、肉体的にも、精神的にも疲れたことと思います。 ★ボールリフティング記録会
☆☆☆ 時間を作って練習してください!! ☆☆☆ ☆クラブ事務所「G-Office」オープン クラブ内外の多くの人たちの協力により、4月18日にクラブ事務所が開設できました。 クラブ事務所の開設は、クラブ運営の効率化と、情報の発信基地としての役割を目的としています。 前者は、指導者会議が毎週木曜日に練習終了後に行われるようになり、事務局会議、役員会が月に1度定期的に開催され、その役割を十分に果たしていると思います。 後者については、クラブ関係者は勿論、地域の少年団をはじめとするサッカー関係者に情報を提供することを目標としていますが、常駐者を置くことができずその方法を検討しなければならないと考えています。 しかし、卒団生が高校生、大学生や社会人になってサッカー選手として、または指導者として行き詰まったとき、事務所の空間(情報)が役立つと信じています。 ★合宿 4月24日~25日に恒例の合宿を行いました。この合宿に新入団員同士、および既団員の交流を図ることを目的としています。 新入団員は、この合宿で交流のネットワークが広がることは実績もあり、今回もそうであったと思います。 しかし、いつも感じることは「合宿が親元を離れることができる、もしくは外泊できる自由な時間」と勘違いし、不可解な行動をする選手が多いことである。 指導者間では、1ヶ月前まではランドセルを背負っていたのだからと慰めながら、今後の成長を期待している。 また、既団員については、先輩としての自覚がなく後輩たちに指導するという場面が見られない。 これは、先輩としての気取りが強すぎる(格好つけ・体裁)場合と、先輩としての能力がない場合があり、これも後輩ができて間もないと理解し、時間が経つとその対処を学習すると期待している。 今回、恒例の社会奉仕(ゴミ拾い)がなかったが、これでは学校や家庭での日頃の姿が表れるものであり、実施できなかったことがとても残念である。 ★GW/分散活動 ゴールデンウィーク(5月の連休)には、県スポーツ少年団大会、丸岡古城カップ、水仙カップと分散して活動をした。 練習試合や紅白戦をはじめゲームは全て、指導員は何らかの形で選手を評価している。選手はこれをもっと意識しなければならない。 1学年上のチームの遠征にいけたから「良い選手」とはかぎらないし、GEMINISの将来のレギュラーが確定されたものではない。また、行けなかったからといって悲観する必要もなく、評価は他方向からされている。 県スポーツ少年団大会は、準公式戦であるのにもかかわらず、これに出場していた3年生はモチベーションが低かったように思われる。 丸岡古城カップに出場できなかったからであろうが、他チームはレギュラー選手が出場しており、同学年の対戦相手に力を出すことができるか、誰がリーダーシップをとれるかがポイントであった。 「モチベーション [motivation] 」とは、英和辞典では「動機を与えること」などの説明があり、「動機」とは、国語辞典では「行動の直接原因・きっかけ」などの説明がある。 モチベーションを上げるときに、「動機を誰が何に与えるのか?」であるが、「指導者が選手に」ではない。 選手自身が、自分の心や身体に対して働きかけなければならないのである。 モチベーションが低いということは、自分がGEMINISを代表してピッチに立っているという自覚や、試合ではチームを勝利に導くためにプレーしなければならないことや、自分の持っている力を出し切り次のステップを狙おうとする「意志力」が欠如していることである。 この意志力を強く持ち続けなければ、個人やチームとして結果を出すことは難しいことになる。 これは、県スポーツ少年団大会に出場した選手だけに伝えているのではない。 ★クラブユース(U-15)県大会・北信越大会 県大会では、優勝という結果が残せたことは大変喜ばしいことであるが、楽に掴んだ優勝ではない。 他チームも負けて良いと思って試合をしているわけではなく、勝つためにGEMINISを研究し戦ってくる。これを受けて立つ余裕がほしい。 「なめてはダメ!呑め!」と言っていることは、相手を過小評価した場合、思った以上の力を出してきたときにパニックに陥りリズムが崩れる。だから決して相手をなめてはいけないのである。 トレーニングに裏付けされた、自信に満ちた態度とプレーで相手に威圧感を与えることが、「相手を呑む」ということである。 どのような相手であっても、心理的スキルの3要素である「集中・冷静さ・自信」を保ち、自分の持っている力を発揮し、自分たちのやるべきサッカーを継続することが必要であり、これをあらゆる試合(紅白戦を含む)で、また、自らの意思で実践することで余裕が持てる選手となる。 北信越大会では、GEMINISの甘さが悪い結果として出たと言える。 1点取っただけで、勝ったような気持ちになりプレーが雑になる。追いつかれてまだ同点なのに負けているような気持ちになり焦る。まさにメンタル面の弱さがゲームに出たと言える。 大会終了後、指導者会では課題を次のような方法で分析し、問題解決に取り組んできた。 【参考】指 導 者 会 で の 課 題 の 分 析 法
その詳細は明らかにしないが、技術・戦術の部分についてはトレーニングで解決を図り、その他の取り組みの一つが学習会の開催であり、高校生との練習試合などである。 これらの成果が、高円宮杯の結果として表れてくることであろうが成果を出すことができるのはピッチに立つことができる選手であるということを、選手自身に分かってほしい。 ★ジュニアユースフットサル北信越大会 ジャッジに恵まれなかった部分もあるが、「もう少し頑張れば北信越代表」という結果である。 この大会での感想は「大会初戦の戦い」および「試合開始直後のプレー」の大切さである。(選手には「試合の入り方」として伝えている) どのチームもどんな選手も大会初戦というものは、何らかの緊張(感)があるのが当たり前である。 初戦の内容が思い通りの試合運びや、選手間のコンビネーションがとれて勝利すると、チームとして弾み(勢い)がつく。 また、個々の選手においては、試合開始直後のファーストプレーが思い通りのプレーができれば、そのゲームは気持ちが乗れるものである。 「初めが肝心」ということであり、大会の初戦や試合でのファーストプレーを重要視し、より大切に(適当ではなく)プレーすることに心掛けなければならない。 幸か不幸かGEMINISは強いというイメージを他チーム(県内に限る)は持っている。[自分達は思ってはいけない。そう思った時点で個人やチームの進歩は止まる] 相手チームにやれるのではないだろうかと思わせると、相手に自信を与えることになるから、技術・戦術あらゆる部分で上位であることを証明するプレーや気迫あるプレーで、相手チームの戦意を喪失させることで、より優位に戦うことができる。 これが、サッカー界で言われている「最初の10分の戦いの大切さ」である。 大 会 結 果
フットサルは、コートが狭いため与えられたスペースがない。スペースがないということは、次のプレーに移るまでの手間暇をかけることができないということであり、時間がないということである。 よって、より正確なボールコントロールと、素早い判断が要求されることつけを加えておく。
★夏休みの取り組み【西日本(U-13)大会/びわこカップ/対高校生練習試合/白馬カップ/くろゆりカップ】 =西日本(U-13)大会= 亀谷コーチの実弟がフレスカ神戸で指導している関係で、第1回西日本(U-13)大会に招待された。 1年生のこの時期にレベルの高い大会に参加できることは幸運なことと感謝しなければならない。 4ヶ月前まではランドセルを背負っていた選手たちは、合宿と同様な意識で行動をしていたのだろうか、若しくは、あれから成長しこの機会を有効に活かし、何かを学び取ってきたのだろうか。 指導者会では、この遠征で一つの指針が決定づけられた。 遠征報告では、「小さいようで大きな差がある」と報告された。プレッシャーのない状態での技術の差はあまり感じないが、レベルの高い試合ではそのような状況でプレーできることは少ない。 京都パープルサンガは、ボールを持った選手へのコンタクト(Contact:接触)が厳しく、自由にプレーをさせてくれない。GEMINIS(石川)の選手は、これに慣れていない。 慣れていないがために、プレーを止めてしまったり、モチベーションが下がることがある。 1期生(現Top)に強さが感じられないのもここにある。 この厳しいコンタクトに慣れる(当然の行為と意識する)ためには、自分たちもできるようになることである。 そこで重要なのは、「アプローチの早さ」である。【Half-time No.19-2 参照】 アプローチ(Approach:寄せ、接近)は、ボールが移動する間に行い、相手がボールをコントロールするときには両足をついて、相手の次のプレーに対処できるようにするという原則があるが、もっと寄せることができるのに止まってしまい、自由にプレーさせるという間合いの問題がある。 また、早さについては、移動するスピードと読みに基づく動きだしがポイントとなる。 これら「間合い」も「読み」も判断が伴うもので、現状で改善されていないことから「チャレンジのプライオリティ(守備の優先順位)」の認識度が低いことが要因と考えられる。 このことから、まず優先順位の1位であるインターセプトを狙うことを徹底することから始まり、厳しいコンタクトと守備を行うことにより、逆の立場に追い込まれても動じない選手(チーム)になると確信する。 =びわこカップ= これについての最初の取り組みが、第2回びわこカップである。 この大会でベンチから指示したことは、「試合の入り方」、「インターセプトを徹底して狙う」、「アプローチ(もっと寄せろ・自由にやらせるな)」、「厳しいコンタクトは当たり前」である。 特にインターセプトに関しては、失敗を恐れずチャレンジする中で、インターセプトを狙えるか否かを試合の中で学習する(感じ取る)こととした。 第一試合の前半には不満ではあったが、試合を重ねる毎に確実に進歩が見られ強さが感じられるようになった。 サンフレッチェ戦では、身体能力の高いチーム(選手)であったが完全に押さえ込み、課題は完璧にクリアし、PK戦で敗れはしたものの高く評価をしている。 この遠征でもう一つ課題としたことが「自主性」である。指導者の指示は特定の3人選手に伝えられこの選手から全員に伝わり、その方法については選手に任され、結果としてできていなければ3人が叱られる。 チーム共通の個人目標/サッカーの個人目標(3)「リーダーシップとフォロアーシップ」である。 =対高校生練習試合= この遠征の翌日に、3年生強化対策[クラブユース(U-15)県大会:問題解決の取り組みに基づく]の対高校生練習試合の1試合目として、金沢桜丘高校(1年生)と行った。 ここでの課題も、相手を上位と認め、自由にプレーさせると失点に結びつく。よって、積極的にインターセプトを狙い自由にプレーをやらせないことと、厳しいコンタクトは当然であり、その中でも自分のプレーを逃げずに行うことである。 この試合の終了後、金沢桜丘高校サッカー部・越田監督からコメントをもらったが、その内容も「ユース(高校生)年代の全国と石川の差は、相手に囲まれた(プレッシャーのかかった)状態であっても正確なプレーができるかどうかである。プレッシャーの無い状態での技術の差はほとんどない。君達の年代からその差を縮めて欲しい。」であった。 =白馬カップ= 白馬カップでは、高円宮杯のエントリー選考も兼ねていると伝えてあるが、春の県スポーツ少年団大会同様、全体としてファイティングスピリットが感じられない。 その中で課題を克服しようと努力している選手もおり、特に目立った選手が1人いた。 内に秘めた闘志が感じられ、自分の持っている力を全て出し切る努力を惜しまず、それで且つサッカーを楽しんでいる。その姿がとても爽やかである。 彼は入団当初から、チームの仕事を積極的にやってくれる選手であり、挨拶もきちんとできることから指導者から高く評価されていた。その選手は「Shintaro-Matsunaga」である。 =くろゆりカップ= くろゆりカップ「兼六園カップ」のエピソードとして、1年生(3期生)が渋川FC(群馬県)の豊島先生にサッカーの講義を受けた。 サッカーゲーム盤の人形を使っての「グッド ボディ シェイプ(Good body shape:良い身体の向き)」がメインであったが、その他の講義の中で重要なポイントは、サッカーに必要な要素「3B/3S」であり、これを覚えて(理解して)おいて欲しい。 3B: Ball control ・Body balance ・Brain / 3S: Skill ・Stamina ・Speed 「3B/3S」のほとんどを答えられた選手がいたことには驚いた。その選手は「Yuji-Machi」である。 ☆村上和哉トレーナー就任 9月の月別活動計画表でも通知しましたが、選手がケガをした場合により良い復帰を目指すため、トレーナーとして村上和哉先生に就任していただいた。 村上先生とのつながりは、石川国体に向けての強化スタッフとして、北村(成年男子2部監督)、三井(成年男子1部アシスタントコーチ)がいたときの国体選抜選手(FW)である。 火曜日を原則として練習会場に来てくださるが、仕事の都合などで毎週とはいかないのでご了承願いたい。来てくださったときには、故障のある選手は自ら相談するように努めてください。 ケガなどの故障を治すのは選手自身であり、医者はそれを助けるものであるということを自覚してください。 〒920-0202 金沢市木越1丁目156‐1 ℡257-8033 / ニック接骨院 ℡257-8029 ★クラブユース(U‐15)新人大会 力あるものが必ず勝つとは限らないのが、サッカーである。だから面白いのである。 しかし、負けるということは相手チームより何かが劣っていたと理解し、結果を謙虚に受け止めなければならない。負けたからと言って卑屈になることはなく、だから何をしなくてはならないかである。 GEMINISとしてやることは変わりなく、カップが一つなくなっただけと思っている。 この大会のビデオを見て検証しているが、一言いわせてもらうならば、びわこカップで発揮した強さ・逞しさが感じられないのが残念である。 さあ、来年のクラブユース(U-15)県大会に向けて、あなたはどのように取り組みますか?
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||