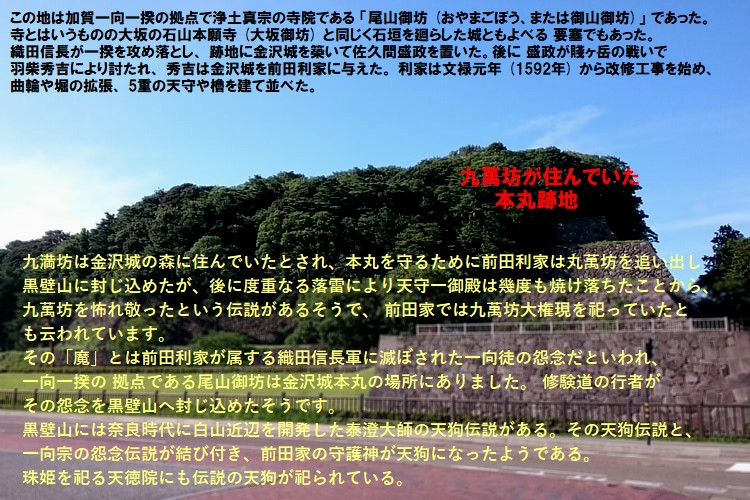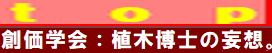
Yahoo 知恵袋から引用
| 浄土真宗の系列に応仁の乱以降 浄土真宗の落ちぶれ寺出身の一向一揆本願寺の蓮如は最大穀倉地帯の加賀百万石の百姓を信仰で手なずけてくれと戦国大名富樫正親に頼まれ 軒を借りて母屋を取ると言う戦国下剋上第一の悪坊主で 5人迄の妻の24人の実子をもうけ 99年独立武装百姓国の初代大名となったが、未だ坊主は禁欲したり破戒坊主を行ったり来たりしていた為 異常性格坊主で、大名なら妾を持ったり三行半を出して離婚したり平気なのに 離婚せず死なして5人目迄現代には いない24人の実子を産ませ、その子孫の信長との和解派は次男が本願寺を継ぐことに決定したが 後に信長が本願寺信者根絶やし寸前で亡くなった後 徳川家康は徳川300年の確固たる封建制度を築く為 長男の強硬派を跡目相続に立てた為 東西本願寺が京都駅周辺に誕生した。 |